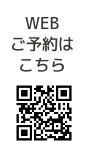2025.08.04
【開催報告】獣医師によるペットの食事療法セミナーを開催しました
【開催報告】獣医師によるペットの食事療法セミナーを開催しました
更新日:2025年8月4日
セミナーの概要
当院では、犬や猫の健康管理に役立つ情報を一般の飼い主さまにわかりやすく伝えるために、「ペットの食事療法」をテーマにしたセミナーを開催しました。
腎臓病・心臓病・肝臓病・膵炎などに対応した療法食の基礎から、実際のフード選びのポイントまで、スライドを用いて詳しく解説しました。
↓からスライドをご覧いただけます。
スライド内容の要約
犬と猫の栄養的な違い
- 犬は雑食に近く、炭水化物の消化も可能
- 猫は完全肉食で、タウリン・ビタミンA・アラキドン酸が必須
- 猫のフードは高タンパク・高脂肪で香りが強く、犬用とは異なる設計
総合栄養食と手作り食
総合栄養食はAAFCOなどの基準に基づいた「これだけで健康維持可能な食事」です。一方、手作り食にはメリットもありますが、栄養バランスやコストの面で注意が必要です。
フードの適正量とカロリー計算
RER(安静時エネルギー要求量)= 70 ×(体重kg)0.75で算出し、活動量などに応じて調整します。特に犬は満腹感が薄いので食べ過ぎやすいため、飼い主の管理が重要です。
病気別の療法食と栄養管理
- 心疾患:ナトリウム・リンを制限し、タウリンやオメガ3脂肪酸を強化。ステージB2以降での療法食導入が推奨。
- 腎臓病:高齢猫に多く、早期の食事管理が進行抑制の鍵。タンパク質・リン・ナトリウムを調整。
- 肝疾患:解毒や代謝機能のサポートが目的。銅制限や高品質なタンパク質を適度に制限して使用。
- 膵炎:急性・慢性いずれも低脂肪・高消化性の食事が望ましい。
複数の病気がある場合のフード選び
心臓・腎臓・膵臓・アレルギー・尿石など、異なる疾患に対応する必要がある場合は、それぞれのメリット・デメリットを考慮し、獣医師と相談しながら優先順位をつけてフードを選ぶことが大切です。
今後のセミナー情報
今後も、ご自宅での注意点や予防医療をテーマにしたセミナーを定期的に開催予定です。

ぜひお気軽にご参加ください。