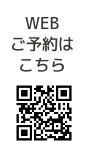2025.08.01
犬の発情について
犬の発情生理とは?周期や兆候、飼い主が知っておきたいポイント
犬の発情生理は、健康管理や繁殖の観点からも非常に重要です。雌犬の発情周期や発情期のサイン、について解説します。
犬の発情周期とは?
最初の発情は、小型犬では生後7~10ヶ月、中・大型犬では生後8~12ヶ月ごろに訪れます。以降は年に1〜2回起こります。小型犬では年に2回、大型犬では1回とされており、個体差があります。犬の発情周期は主に以下の4つの段階に分けられます。
1. 発情前期
- 期間:7〜10日程度
- 症状:外陰部の腫れ、出血(ピンク色または赤い分泌物)
- 行動:オス犬に興味を示されるが、交尾を拒否する
2. 発情期
- 期間:5〜14日程度
- 症状:出血が少なくなる、外陰部が柔らかくなる
- 行動:交尾を受け入れる、オス犬に積極的になる
3. 発情後期
- 期間:約2ヶ月
- ホルモンバランスの変化により、妊娠していなくても妊娠したような状態になる「偽妊娠」が見られることがあります。
- この時期は、特に「子宮蓄膿症」の発症リスクが高くなるため注意が必要です。
子宮蓄膿症に注意
子宮蓄膿症は、発情後期にホルモンの影響で子宮内に細菌が繁殖し、膿がたまる命に関わる疾患です。特に避妊していない中高齢のメス犬に多く見られます。
以下のような症状が見られた場合は、すぐに動物病院を受診してください:
- 元気や食欲がない
- お腹が張っている
- 陰部から膿のような分泌物が出る(ただし「閉鎖型」では出ないことも)
- 水を大量に飲み、おしっこの量が増える
- 発熱・震え・嘔吐など
子宮蓄膿症の治療は、緊急の子宮・卵巣摘出手術が主となります。早期発見が命を救う鍵です。
4. 無発情期
- 期間:2〜10ヶ月(個体差あり)
- ホルモンの活動が休止状態になります。
発情期のサインと行動変化
発情中の犬には以下のような行動の変化が見られることがあります。
- 落ち着きがなくなる
- 頻繁に外陰部を舐める
- マーキング行動が増える
- オス犬に近づきたがる
こうした変化を見逃さず、ストレスをかけないように過ごさせてあげることが大切です
避妊手術と発情・病気予防の関係
避妊手術を受けた犬は、発情が起こらなくなるだけでなく、子宮蓄膿症や乳腺腫瘍の予防にも効果的です。初回の発情前(生後6〜8ヶ月頃)に手術を行うことで予防効果が高まるといわれています。
避妊手術のタイミングやメリット・デメリットについては、当院の獣医師までご相談ください。
まとめ
犬の発情生理を理解し、適切に対処することは、健康的なペットライフの第一歩です。特に発情後期には「子宮蓄膿症」のリスクがあるため、体調の変化を見逃さないことが重要です。
当院では、避妊・去勢手術や発情期の行動相談も行っております。気になる症状がある場合は、お早めにご相談ください。
獣医師清水